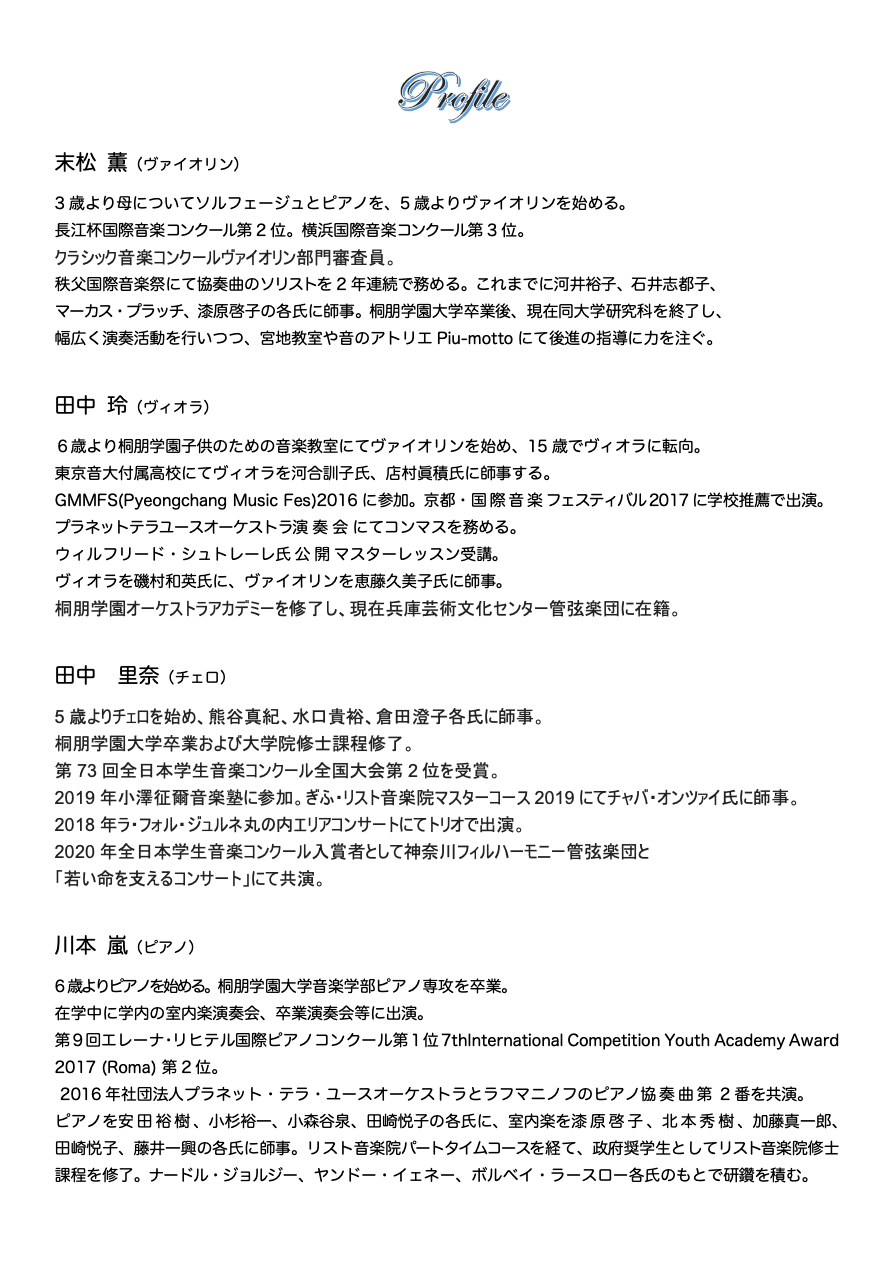楽器のもつ教育力 ②ヴァイオリン
加速度的にAI化が進むこれからの社会の中で、「人間にしかできないこと」としてクローズアップされるのが、芸術活動です。
この心の領域こそ、豊かな人生を構築していくうえで何よりの支えになります。
特にヴァイオリンは素朴なメカニックゆえ、一から音を作りあげていく難しさと、根源的な響きの体験を与えてくれます。最初から左右の手の協調を求められるという意味で、あまり小さいうちは難しいですし、感覚的に動きの組合せを習得するという意味では手遅れになる臨界期があります。個々人にとって丁度良い年齢を見極めてレッスンを開始することが、とても大切です。
もし、お子さんがヴァイオリンに興味をしめしたら、まずは体験レッスンをお勧めします。教師は、開始時期とレッスン内容に関して適切なアドバイスをするはずです。
一方でピアノとは異なり、体格に合わせて楽器の大きさを選ぶので、その意味では早期教育に向いているとも言えます。
また弦楽器は、楽器の品質レベルによって大きく音質が異なります。必ずしも高額である必要は有りませんが、相性の良い、心地よい響きの楽器を選ぶことが肝要です。弾き手の耳の良さの1~2歩先をいく性能が、丁度良いと言われます。逆に楽器の性能が弾き手に比して低すぎた場合、耳を育てる機会を失うことになりかねません。(続く)